どうもよよよです
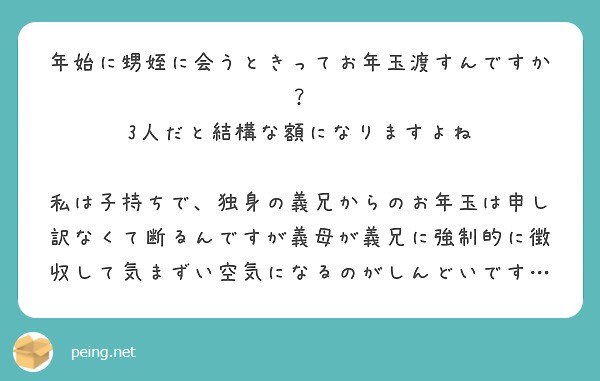
姪はまだお年玉をあげる歳ではないのであげてないです
お年玉をもらうことで気まずい気持ちになるなら、その義兄の誕生日に義母には黙って、もらったお年玉と同額のギフトカードでも毎年贈るようにしたらどうですか?それで金銭的な貸し借りはなしでしょう、義兄の顔を立てつつ義兄もお年玉の折に機嫌を損ねるようなこともなくなると思います
僕も非常に貧乏のためできればお年玉をあげたくないのですが、頑固にあげないとわたしがますます家族内で孤立するのを恐れた祖母つまりわたしの母親が「これ、よよよおじちゃんからだよ」などと勝手に僕からだと言って
お年玉を包むようなことをしてしまう人なので、少額でもあげないとかえって面倒なことになるでしょうね、しかもできるだけケチだとバレないようにしたほうがむやみに嫌われずに済むでしょう
そこで来たるお年玉をあげるというXデイに備え出費を少額で済ますためにお年玉ゲームというのを考えつきました、封筒を20枚くらい用意してその中にそれぞれ1000円〜3000円ぐらいのお金を入れておいてこう言うのです
さぁお年玉ゲームだよ!1000円〜2万円のお金を封筒に入れておいたからどれか1枚選んで!半分以上は一万円以上だから奮発したよ〜
「え!最高二万円!?」と子どもたちは目を輝かせて選ぶも当然千円を引く
あれ、ざんねん!それはかなり運が悪いよ、ゲームだからしかたないね、はい千円、いい子にしてたら来年は二万円当たるからね!
と甥と姪にいうのです、そうあくまで選んだのは自分
自己の判断によって掴み取った結果である以上、ふだんひとりで大分県に住んで何をしているか分からない謎のおじさんには文句を言うことはできません
もし甥と姪に知恵がついてきて、「おじさん、残りの封筒を見せてよ!」などと言ってきたら「そんな人を疑うような悪い子にはお年玉ゲームはなしだ!」と怒る素振りをしながら素早く封筒を回収します
子どもたちもゲーム的で楽しいし、いい子にしてたらきっと当たるんだと教育的な内容を含んでいるし、大分のおじさんも事実では毎年奮発してるけど運が悪いだけ、という事実で体裁を保てるし誰にとっても素晴らしいアイデアだとは思いませんか?
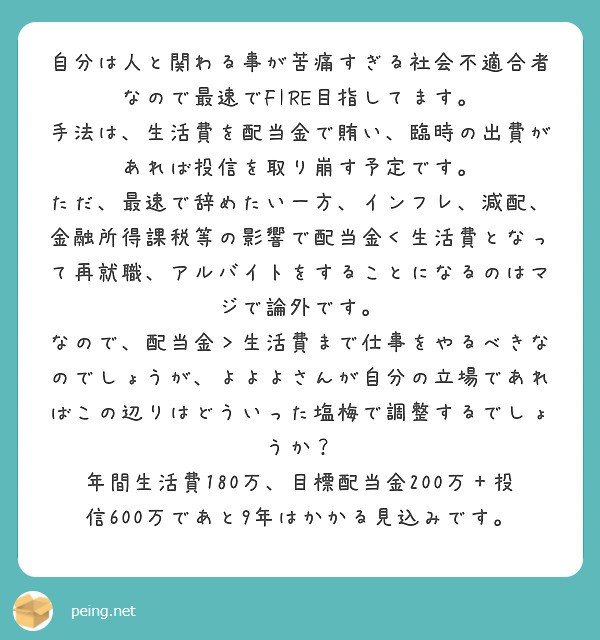
インフレひとつとってみても何一つ確実なことは言えない
投資でインフレ対策を100%全て賄おうとするのは無理、株式などのリスク資産がある程度物価にも連動する性質があるからリスクヘッジにはなるというだけでそれで完全に十分ではない
物価が上がっても働き手不足倒産が増えれば平均株価は落ちるでしょうし、スタッグフレーションに陥れば物価だけは上がり給料が増えない景気は上がらない、株価も上がらない状態に陥る、そうなればリタイア民がよく言う「インフレ対策は株などのリスク資産に投じているので大丈夫ですw」←こいつバカです、という事態になります
どういう塩梅でやりますかと言われても、おっしゃる通り減配や増税なんかもこっちで全て予想立てられるわけない、意味がない
家賃も追い出されるかもしれないし病院の医療費負担割合も変わってるし年金も当然変わってる、病気にもなってるし足が悪くなって車も必要、寂しくなってSNSロマンス詐欺で3000万円くらい取られてるかも、今の生活費はこうだから将来は物価が2倍になっても何年まで大丈夫〜とかムダ、全て不確定要素しかないのに何を計算できる気でいるの?
だらだらとした逃げ切り計算をしてみた!みたいな記事はほかのリタイアブロガーがやりがちだけどムダだな〜と思ってみてる、小細工弄してかりそめの安心感得ようとしてるね〜
そんな予想にもなってない将来の予想は全て無駄です、リタイア民こそ将来のちまちまとした計算なんかより精神論を構築すべき、社畜が精神論で働くのがダメなのは他人の利益のためだから、自分のためなら精神論というのは最重要項目なんですよ
死んでもいいからその間の自由を楽しみたいという気概こそ重要
そのうち杵築橋の下で冷たいふやけた人が発見されて魚の餌になるだけだな、それまでは楽しもう、と自分の命を割り切ってください、リタイアするならそういう覚悟が必要です
無職の精神論ならこのブログで学ぶのが最適解なので過去記事などを参考にその性根を叩き直してください
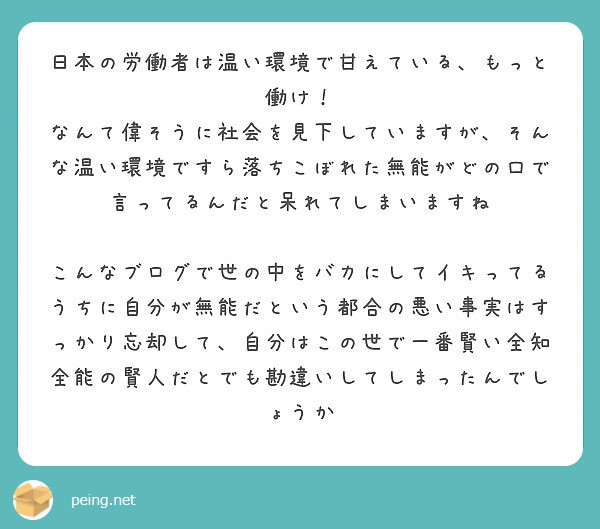
学びの窓が閉じてるな〜
俺が無能だとして世の中がクソじゃない理由にはならない、無能だから黙ってろという謂れもない、あらゆる立場の人がその立場で感じることを発言するべき
忘却なんかしてない、自分は無能で仕事は全くできなかった、しかし世界一勤勉だと言われてる日本人が生産性が低いヌルい仕事してるのは事実だし実は世界一働いてるふりがうまいだけの民族だということは世界中にバレてきてる、だからもっと働けよ、と言われるのは当然
自身のやってることについて自覚しなさいということ、自覚という意味では俺は世の中の有能ぶってる奴らより出来てる
なまじ有能だったらこの世界のクソさに気づけなかったかも、とも思う、無能だからこそ到れる境地がある、気づけることがある
「無能のくせになにを偉そうに語るなよ!」ではなく無能というジャンルにおいてある程度の経験を積んだ先生と思ってほしい
学びの窓を開けよう、あらゆることから学ぶ意識を持とう